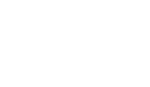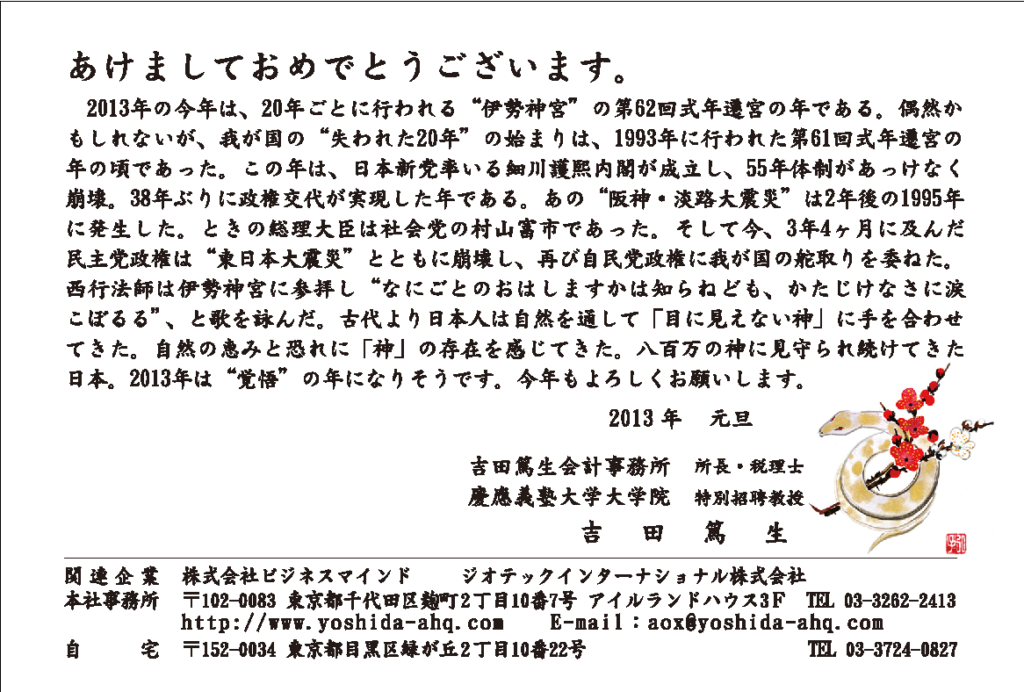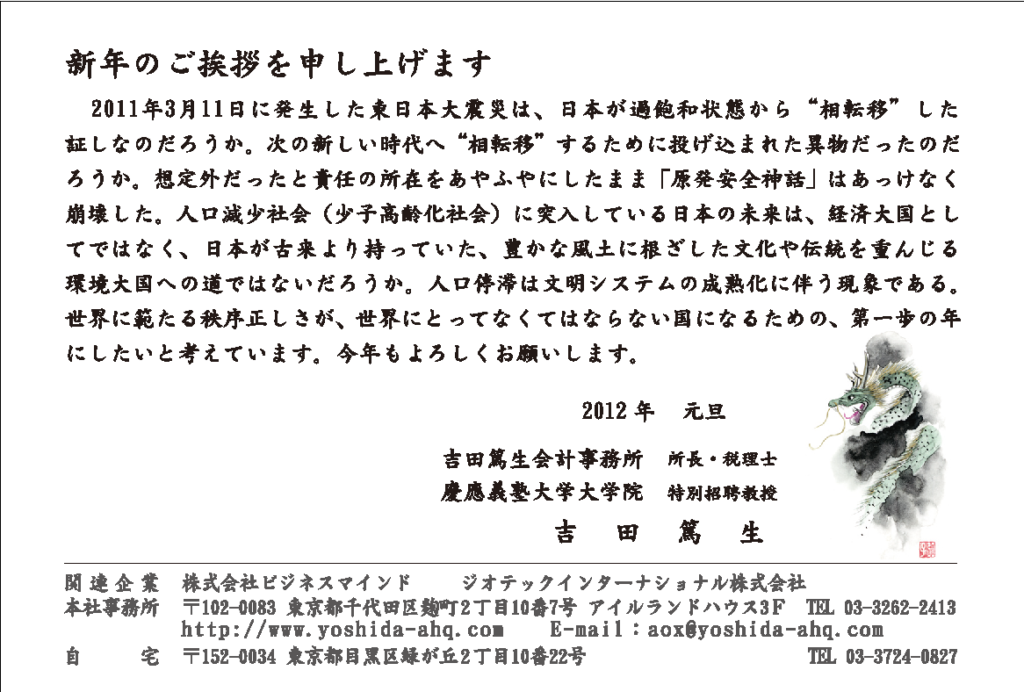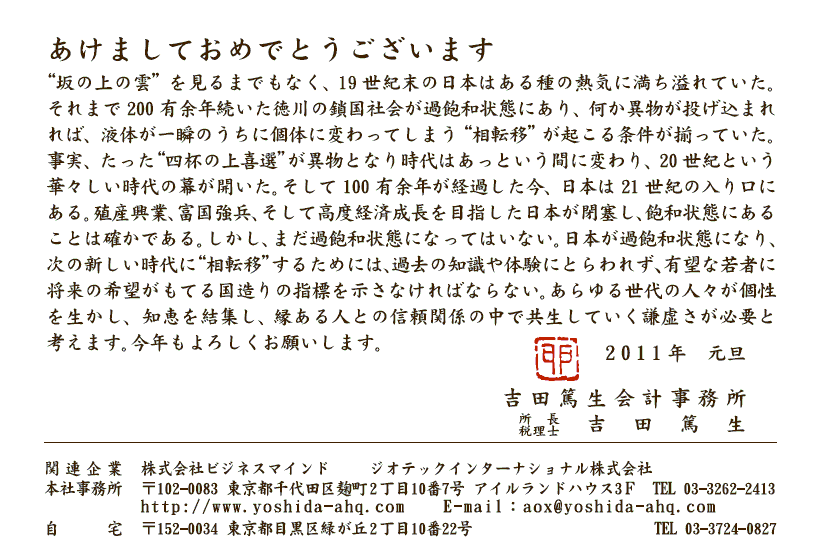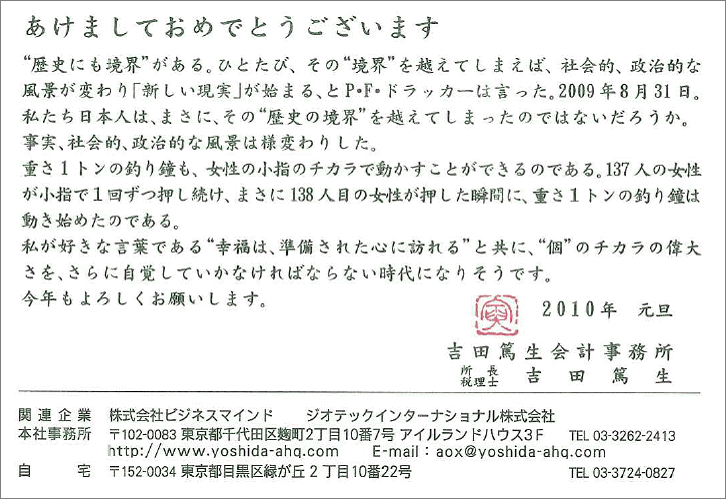“文明の成熟と人口減退社会の訪れは、人口と資源、あるいは人口と環境など様々な側面で、日本社会が均衡状態に立ち至ったことを意味する”と鬼頭宏氏は、彼の著書「2100年、人口3分の1の日本」で述べている。経済学者シュンペーターは、均衡状態とは沈滞した社会を意味する、と「経済発展の理論」の中で説いている。沈滞した社会を新たに発展させる役割を担うのは起業家であり、その起業家たちがイノベーションを実行し「創造的破壊」をするのである。
世界に先駆けて少子・高齢化と人口減少社会の先頭に立つ日本は、美しい環境づくりを21世紀イノベーションとして、世界の人々が羨むような「美しい国づくり」を目指す絶好の機会とも言えるのではないだろうか。出生率が下がり人口増加が抑制されたのは、我々人類が潜在的に有している“自動調整メカニズム”が無意識のうちに働いた結果ではなかろうか。財政的にも効率がよく、環境負荷の小さなライフスタイルを、もう一つ進んだ次元で調和させた社会。それは経済成長を通じて量的拡大を求める大量消費社会ではなく、精神的な豊かさや生活の質を大切にする未来社会の姿ではないだろうか。少なくとも、その未来社会は日本に遅れて「少子・高齢化社会」が訪れることが約束されている中国やインドのよきモデルとしての未来社会であるべきではないだろうか。
2013年 1月 吉日
吉田篤生会計事務所
所長 吉田 篤生
日本経済新聞(2011/06/25)によれば、中国は2050年をメドに標準的な原発を400基以上稼働させる長期エネルギー構想を発表したという。考えてみれば、我が国は、人口1億2千万人の電力需要を賄うために54基の原発を建設し稼働させているのである。人口13億人を超える中国の電力事情を賄うために400基の原発を必要とするのは、あたりまえといえば、あたりまえのことだろう。言うまでもなく、我が国は、中国に建設される原発の風下に位置する国である。中国に建設された原発の一基にでも事故が発生すれば、事故原発から飛散する放射性物質は偏西風に流され、黄砂と共に我が国の全域に到達する。
福島原発の事故により、我が国の世論は“脱原発”へとエネルギー施策の転換を要求している。しかし原発の問題は、我が国だけのローカルな問題ではなく、グローバルな観点からとらえざるを得ない問題ではないだろうか。我が国が有する原発建設や維持メンテナンスや安全対策などのノウハウを、“脱原発”という大義名分で枯渇させるべきではない。少なくとも、中国の長期エネルギー構想に対して、技術支援、経済支援、とあらゆる支援の手をさしのべていくべきではないだろうか。過去の歴史を紐解いてみるまでもなく、日中間の友好関係を築き上げることが東アジア、ひいては環太平洋社会の安寧への道ではないだろうか。
2012年 1月 吉日
吉田篤生会計事務所
所長 吉田 篤生
高齢化社会と多様化社会は同じベクトル上にあるという。なぜなら、“人間の若さは一般に社会を均質化し集団化させる条件であるが、老いの経験は、ただそれだけで、すでに個人の運命を多様化し、個別化する方向に働くからである”と山崎正和は、彼の著書「柔らかい個人主義の誕生」で述べている。20歳の青年は、誰しも同じように性的に成熟し、体力の点で生涯の頂点にあり、配偶者の獲得と生計の自立を目指すという共通の課題を抱えているが、老年が抱える課題は一人一人異なり、60歳で衰弱の域に入る人間もいれば、80歳で矍鑠(かくしゃく)と活躍している人物もいる。
20世紀末、組織に全面的に依存していた個人のアイデンティティが落ち着く先を求め、さまよい始めて、はや10有余年。人間とは“その人が持っている関係の総和である”と内山節は、哲学した。2011年は“関係の総和”を今一度、問い直し、見つめ直していく年にしたいものである。
引用文献:「柔らかい個人主義の誕生」山崎正和著/中公文庫
2011年 1月 吉日
吉田篤生会計事務所
所長 吉田篤生
我が国は世界でも類をみない、すばらしい風土資源を有する国です。四方を海に囲まれ、その海から立ち昇る水蒸気が3,000m級の山々にぶつかり、雨となり森に注がれ、川となり、大地へ水を分配しながら海に還り、再び水蒸気となって昇っていくという循環が日本のどこででも行われています。人間の経済活動が、世界的な資源枯渇を招いている地球上において、我が国は、国土面積の66%の森林率を保持し、人工林に限って言えば、世界の森林資源の12分の1を有するという森林資源大国なのです。
地球温暖化防止策の切り札として森林のCO2吸収力が注目されています。限りある化石エネルギーに代わる持続可能なエネルギーとして、太陽エネルギー、そしてバイオマスエネルギーが見直されようとしています。アーサー・C・クラークの「2010年宇宙の旅」は、ボーマン船長に“Something Wonderful(何か素晴らしいことが起きる)”という言葉を託して幕を閉じた。そして、その2010年がやってきた。
少なくとも私たち日本人は、風土という再生可能な資源を有していることは確かである。エネルギーと食料の自給率を高めることは可能ではないだろうか。過去の歴史を紐解いてみても、エネルギーと食糧の自給率を高めた国が、衰亡したという歴史を見聞したことはない。
2010年 1月 吉日
吉田篤生会計事務所
所長 吉田篤生